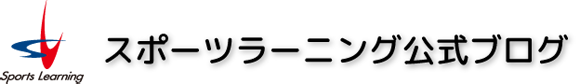Speaks vol.231
<<脳から体への指令がデュアルタスク処理する決め手>>
前回のスピークスでは、「デュアルタスク」について取り上げました。
結論から言うとテニスは、
最低でも2つ以上を同時並行処理する必要のある「デュアルタスク」のスポーツです。
ボールを見ながら走る。
コースを狙いながら打つ。
打ちながら次のポジションを想定する。
ところが打ったら打ちっぱなしで、
次のポジションへ移動できないプレーヤーが少なくないという話をしました。
それは、「デュアルタスク」のトレーニングができていないから。
ボールを打つ「シングルタスク」と、
次のポジションへ移動する「シングルタスク」とを同時並行処理できるようにならないと、
一つひとつのタスクは練習で別々にできたとしても、
ゲームではそれぞれがつながらない問題に直面します。
とはいえ、「デュアルタスク」も「シングルタスク」の集まりです。
ですからトレーニングすれば、できるようになります。
そしてできるようになるか、ならないかは、
運動神経の「ある・なし」ではなくて、
トレーニングを「する・しない」の違い。
前回紹介した、たとえば右手のひらで右ももをスリスリしながら、
左手のこぶしで左ももをトントンたたきます。
あるいは左右の手で必ず右手が勝つじゃんけんをします。
「デュアルタスクトレーニング」に慣れていないと、
左右が同じ動きや形になってしまうのでした。
こういった遊びだと間違えても「アレレ?」とおどける笑い話で済むけれど、
いざテニスのプレーに話が及ぶと、
「下手くそ」「運動神経がない」などと、
自分を(あるいは他人を)ネガティブに責めてしまいがちです。
そうして脳がストレスにさいなまれると、
高度な「デュアルタスク処理」は、ますます難しくなってしまうでしょう。
そしてテニスは体を使ってプレーするといっても、
指令を出すのは脳である以上、
「デュアルタスク」は行動だけではなく、思考についても、
その傾向性について指摘できるかもしれません。
たとえばテニスの試合で負けた生徒さんに敗因を尋ねると、
「相手のボールが強かったです」「全然ミスしなかったです」などと、
一面的な振り返り方になるプレーヤーがいます。
とはいえテニスは、「自分より強いボールを打つ相手には、絶対勝てないのか」
「ミスしない相手のミスを誘える配球は存在しないのか」など、
多面的にも考えられるでしょう。
相手の強いボールを受けながら、
自分がアドバンテージを掌握するにはどうすればいいのかの、
2つのテーマについて同時並行処理します。
もちろん一つひとつの思考は「シングルタスク」なのだけれど、
それらを寄せ集めて密度を高めると「デュアルタスク」、
あるいは「マルチタスク」になります。
たとえば、戦況や自分の技量にもよるけれど、
「相手の強いボールを受けながら、自分はカウンター処理する」
「ミスしない相手のプレーをしのぎながら、自分は単調にならないように緩急をつける」
などが考えられるかもしれません。
これらも「ながら処理」のひとつの形であり、
「デュアルタスク」になっています。
すると自分より強いボールを打ってくる相手や、
なかなかミスしない相手にも善戦できたり、
勝てたりする可能性が高まりもします。
少なくとも「相手のボールが強かったです」
「全然ミスしなかったです」などと一面的に考えるよりは、
生産的であるに違いありません。
「自分より強いボールを打つ相手にはカウンター対応」
「ミスしない相手のミスを誘う緩急の使い分け」などを、
テニスをプレーしながら考えるのは、
思考と運動の同時並行処理を司る頭と体による「デュアルタスク」であると言えます。
次回は「デュアルタスクの達人」について紹介しながら、
さらに多面的なものの見方、考え方、行動について理解が深まる内容を考察してみます。
解説/スポーツラーニング・黒岩高徳
構成/テニスライター・吉田正広
さあ、このSpeaksを読んだらさっそく練習しましょう!!レッスンへGO!!
休日レッスンお申し込みページ
平日レッスンお申し込みページ
ナイターレッスンお申し込みページ
早朝レッスンお申し込みページ