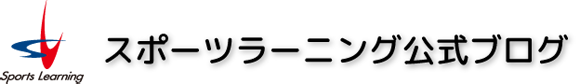Speaks vol.237
<<労力を再配分して「認知」「判断」能力を上げる>>
相手から飛んできたボールについて「認知」し「判断」する。
それは、打ち返す前に行なわなければなりません。
「ボールを打つためのプロセス」について、
前回のスピークスでは上記のことを説明しました。
これをすっ飛ばして「ただ打つ」だけになると、
手に入れたいナイスショットの「結果」は得られません。
「結果」を得るためには、
しかるべき「プロセス」を踏む必要があります。
打ち返すスイングは、
自動車の運転でいえばハンドルを切る最後の操作。
その前に、見通しの悪い状況を「認知」して、
右折できるか「判断」するプロセスがなければなりません。
テニスが上手くいかないプレーヤーは、
見通しも対向車も確認せずにハンドルを切るようなもの、
とたとえました。
とはいえテニスの場合は、
相手がボールを打ってからこちらへ飛んでくるまでの時間が短く、
状況を「認知」して「判断」するスピードを可及的に上げなければ、
上手く対応できません。
トッププロが繰り広げるすさまじいラリーは、
ボールのスピードにばかり目を奪われがちだけど、
観客の目には映らないプレーヤーの脳内で行われる、
超高速な「認知」と「判断」による賜物なのでしたね。
それが少しずつでもできるようになるための具体的な取り組みが、
前回の最後に少しお伝えした「労力の配分」です。
自分が持っている労力を配分するうえで「打つこと」、
あるいは「打ち方」に、
そのエネルギーの多くを使いすぎてはいないでしょうか?
しかし自分の打ち方はいくら労力を注いでも、
今すぐには変わりません。
勉強しなければ、成績が変わらないのと同じです。
そうであるにもかかわらず、
今の実力以上のパフォーマンスを出そうとするあまり、
打つこと、打ち方に、全力を費やしてしまう傾向性が見て取れるのです。
そのせいでかえって、
今の実力以下のパフォーマンスしか発揮できずにいる。
そこで今回は、「ボールを打つことを頑張りすぎない」というご提案。
打つことや打ち方に労力を使いすぎると、
相手がどのポジションにいてどんな体勢になっているのか、
あるいはどんなボールが飛んできているのかなどに意識が及ばないから、
状況を「認知」して「判断」する余裕がなくなるのです。
それは、見通しや対向車を確認せずに、
焦ってハンドルを切るようなプレー。
そのような感じで、自分が打つこと、自分の打ち方ばかりを、
意識しすぎていないでしょうか。
そして打つこと、打ち方に労力を使いすぎるプレーヤーは、
たいてい「打ち急ぐ」傾向です。
だから打球タイミングが合わずに、ミスしてしまう。
よく「ボールを待てません」とは言うけれど、
それはプロセスが間違っているのです。
そうであるにも関わらず、
ミスした原因はラケットワークやフォームなどの不備にあると考えがち。
そうすると打つこと、打ち方にますます労力を費やす悪循環だから、
打ち返すよりも先に踏まえなければならないはずの、
飛んでくるボールを「認知」し「判断」するプロセスがすっ飛んで、
さらに、もっと、打ち急いでしまうのです!
なので打つこと、打ち方に費やす労力を減らし、
「認知」と「判断」へ労力を再配分する。
言い方を変えれば、打つことを頑張りすぎず、
打ち方について意識しすぎなければ、
エネルギーは必然的に残るから、
「認知」し「判断」する余裕が、自然と生まれてくるのです。
私たちのエネルギーは有限ですから、
状況に応じて適切に振り分けるバランスが大事ですね。
なかなかテニスが上達しない理由は、
打つことを頑張りすぎて、
打ち方について意識しすぎていたからかもしれないというパラドクス。
「認知」し「判断」するという、
ボールを打つために必要な「プロセス」を経れば、
今まで打ち急いでいたプレーヤーもボールをちゃんと待てるから、
手に入れたいナイスショットの「結果」も得やすくなるはずです。
解説/スポーツラーニング・黒岩高徳
構成/テニスライター・吉田正広
さあ、このSpeaksを読んだらさっそく練習しましょう!!レッスンへGO!!
休日レッスンお申し込みページ
平日レッスンお申し込みページ
ナイターレッスンお申し込みページ
早朝レッスンお申し込みページ